「自分には価値がない」「どうせ何をやってもうまくいかない」そう感じて、一歩を踏み出すことをためらってしまった経験はありませんか。その生きづらさの背景には、自己肯定感の低さが関係しているのかもしれません。
自己肯定感が低い人の特徴として、常に他人と比較して落ち込んだり、過去の失敗を引きずったりすることが挙げられます。このような状態が続くと、仕事や恋愛など、人生のあらゆる場面で悪影響が及ぶ可能性があります。
では、自己肯定感が低いとどうなるのでしょうか。また、その根本的な原因はどこにあるのでしょう。一部には、幼少期の親との関係が原因となっているケースや、傷つくことを恐れるあまりプライドが高い状態になってしまっている場合も考えられます。
この記事では、なぜ自己肯定感が低くなってしまうのか、その原因を深く掘り下げるとともに、今日から実践できる自己肯定感を高めていく方法を具体的にお伝えします。自分を認め、より軽やかな毎日を送るためのヒントがここにあります。
記事のポイント
- 自己肯定感が低くなる根本的な原因と特徴
- 自己肯定感の低さが人生に与える具体的な影響
- 思考の癖を変え、自己肯定感を育むための実践的な習慣
- ありのままの自分を受け入れ、前向きになるための考え方
なぜ?自己肯定感が低い状態に陥る原因とは
- 当てはまる?自己肯定感が低い人の特徴
- 自己肯定感が低いとどうなる?起こりうる問題
- 自己肯定感が低くなる根本的な原因
- 自己肯定感が低くなる原因は親との関係も
- 自己肯定感の低さが恋愛に与える影響
- 意外?プライドが高いことも一因に
当てはまる?自己肯定感が低い人の特徴

自己肯定感が低い人には、いくつかの共通した思考や行動のパターンが見られます。これを理解することは、自分自身を客観的に見つめ直す第一歩となります。
まず挙げられるのは、「他人軸」で物事を考えてしまう傾向です。例えば、会議で発言する際に「間違っていたらどうしよう」「否定されたら怖い」と過度に他人の評価を気にしてしまい、結局当たり障りのない意見しか言えなくなります。自分の「どうしたいか」よりも、他人に「どう思われるか」を優先するため、常にプレッシャーを感じ、精神的に疲弊してしまうのです。
また、自分に対して無意識にダメ出しをする癖も特徴の一つです。「どうして自分はできないんだろう」「あの人に比べて自分は…」と、他人と自分を比較しては落ち込み、自己嫌悪に陥るという負のループを繰り返します。
さらに、「~しなければならない」という口癖が頻繁に出ることもあります。これは「社会の常識」や「こうあるべきだ」という、自分が作り出した架空の規範に縛られている状態です。そこには自分の本当の気持ちは存在せず、見えない誰かの目を気にして行動してしまっているのです。
これらの特徴に心当たりがある場合、まずは「また他人軸で考えているな」「今、自分にダメ出ししたな」と、自分の思考パターンを自覚することから始めるのが大切です。
自己肯定感が低いとどうなる?起こりうる問題

自己肯定感が低い状態が続くと、日常生活のさまざまな場面で具体的な問題が生じる可能性があります。精神的な負担が増えるだけでなく、人生の選択肢を狭めてしまうことにもつながりかねません。
最も大きな問題の一つは、精神的な疲労感が常に付きまとうことです。他人の評価を気にし、自分を責め続けることは、心に大きな負荷をかけます。会社や学校から帰宅した後、どっと疲れが出たり、他人のSNSを見て楽しそうな様子と自分を比較して落ち込んだりするのは、このためです。オンとオフの切り替えがうまくできず、心が休まる暇がありません。
また、挑戦することへの恐怖心が強くなり、新たなチャンスを逃しがちになります。失敗を過度に恐れるため、「自分には無理だ」と行動する前から諦めてしまうのです。これは、キャリアアップの機会や新しい人間関係を築くチャンスを自ら手放していることと同じです。
人間関係においても、コミュニケーションが円滑に進まないことがあります。相手の些細な言動をネガティブに捉えてしまったり、嫌われることを恐れて本音を言えなかったりするため、表面的な付き合いになりがちです。
このように、自己肯定感の低さは、単なる「気の持ちよう」の問題ではなく、心身の健康や人生の豊かさに直接影響を及ぼす、見過ごせない問題であると考えられます。
自己肯定感が低くなる根本的な原因

自己肯定感が低くなってしまう背景には、いくつかの根本的な原因が考えられます。これらは一つだけではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。
中心的な原因として挙げられるのが、自分の価値を測る基準が自分の中ではなく、他人の評価や外部の基準にある「他人軸」の状態です。自分の行動や選択の正しさを、他人の反応や社会的な成功、他者との比較によって判断しようとします。このため、他者から否定されたり、誰かと比べて劣っていると感じたりすると、自分の価値そのものが揺らいでしまうのです。
また、過去の失敗体験がトラウマとなっているケースも少なくありません。例えば、過去に誰かから言われた何気ない一言が心に深く刻み込まれ、「自分はダメな人間だ」という思い込みを強化してしまうことがあります。人間の脳は、褒められた経験よりも、否定されたり批判されたりしたネガティブな経験の方を強く記憶する傾向があるため、意識的にポジティブな側面に目を向けない限り、自己評価は下がる一方になってしまいます。
さらに、完璧主義の傾向も自己肯定感を下げる一因です。常に完璧でなければならないという高い理想を掲げ、少しでも達成できないと「自分は能力が低い」と結論づけてしまいます。しかし、常に完璧でいることは不可能ですから、結果として自分を責め続けることになります。
これらの原因を理解し、自分の思考がどのようなパターンに陥っているのかを客観視することが、自己肯定感を取り戻すための重要なステップとなります。
自己肯定感が低くなる原因は親との関係も

自己肯定感の形成には、幼少期の経験、特に親との関係性が深く影響していると考えられています。もちろん、全ての原因がそこにあるわけではありませんが、人格の土台が作られる重要な時期の経験は、その後の自己評価に大きな影響を与える可能性があります。
例えば、親から「甘えるな」「あなたはのろまなんだから」といった言葉を頻繁にかけられたり、他の兄弟や友人と比較されたりする環境で育った場合、子どもは「自分はありのままで愛される価値がない」と感じてしまうことがあります。テストで良い点を取った時だけ褒められるといった、条件付きの愛情を受け続けると、「何かを達成しなければ自分には価値がない」という価値観が刷り込まれてしまうのです。
また、褒められた記憶がほとんどないというのも、自己肯定感を低くする一因です。子どもは親からの肯定的なフィードバックを通じて、「自分はこれでいいんだ」という感覚を育んでいきます。この経験が不足すると、自分に自信を持つことが難しくなり、常に他人の評価を求めるようになってしまいます。
親が離婚した経験なども、「自分のせいでこうなったのではないか」と、子どもが自分を責めるきっかけになることがあります。
ただし、ここで重要なのは、過去や親を責めることではありません。過去の経験が現在の自分にどのような影響を与えているのかを客観的に理解し、「それは過去の出来事であり、今の自分の価値を決めるものではない」と切り離して考えることが大切です。過去は変えられませんが、過去の出来事に対する解釈は、今からでも変えていくことが可能です。
自己肯定感の低さが恋愛に与える影響

自己肯定感の低さは、恋愛関係においてもさまざまな課題を生み出すことがあります。自分に自信がないことからくる不安や恐れが、パートナーとの健全な関係構築を難しくしてしまうのです。
まず、相手の愛情を常に疑ってしまう傾向があります。パートナーが「好き」と言ってくれても、「リップサービスではないか」「本当はそう思っていないはずだ」と素直に受け取ることができません。自分自身が自分の価値を信じられていないため、他人が自分を愛してくれるという事実を受け入れるのが難しいのです。これにより、相手の言動を逐一チェックしたり、愛情を試すような行動をとってしまったりして、関係を悪化させる原因になります。
また、パートナーに過度に依存してしまうケースも見られます。自分の価値を自分自身で見出せないため、パートナーからの評価や存在そのものに自分の価値を委ねてしまいます。その結果、相手に嫌われることを極度に恐れ、自分の意見や感情を抑え込み、何でも相手に合わせてしまうようになります。これは健全な関係ではなく、精神的な負担が大きくなるばかりです。
逆に、相手を束縛したり、過度に嫉妬したりすることもあります。これは「自分はいつか捨てられるかもしれない」という見捨てられ不安からくる行動です。自信のなさが、相手を信じられないという気持ちにつながり、結果としてお互いを苦しめることになります。
幸せな恋愛を築くためには、まず自分自身が自分の価値を認め、一人の人間として自立していることが基盤となります。
意外?プライドが高いことも一因に

自己肯定感が低いことと、プライドが高いことは、一見すると正反対の性質のように思えるかもしれません。しかし、実はこの二つは密接に関連している場合があります。この場合のプライ-ドが高い状態とは、ありのままの自分を守るための「防衛的なプライド」と言えます。
自己肯定感が低い人は、自分の弱さや欠点を受け入れることができず、傷つくことを極度に恐れています。そのため、「自分は本当はすごい人間なんだ」「自分は間違っていない」という鎧を身にまとい、他人からの批判や指摘を過剰に拒絶しようとするのです。これが、プライドが高いという形で表れます。
防衛的なプライドの具体例
- 間違いを認められない: 自分のミスを素直に謝ることができず、言い訳をしたり他人のせいにしたりします。間違いを認めることは、自分の無能さを認めることだと感じてしまうからです。
- 人からのアドバイスを聞き入れない: 他者からの助言を、自分への批判や攻撃だと捉えてしまいがちです。そのため、素直に耳を傾けることができません。
- 自慢話が多い: 自分の実績や能力を過剰にアピールすることで、「自分は価値のある人間だ」と周囲に認めさせようとします。内面の自信のなさを、外面的な成功で補おうとする行動です。
このように、一見強気に見える態度は、実は内面の脆さの裏返しなのです。このタイプのプライドは、真の自信からくるものではないため、人間関係のトラブルを引き起こしたり、自分自身の成長を妨げたりする原因となります。
本当の意味で自分を大切にするためには、この脆いプライドを手放し、自分の弱さや不完全さも含めて受け入れる勇気を持つことが求められます。
自己肯定感が低い状態から抜け出す実践的なヒント
- 自己肯定感を高めていく方法の基本
- 思考の癖をリセットする簡単な習慣
- ネガティブな感情との上手な付き合い方
- ありのままの自分を受け入れる自己受容
- 自己肯定感が低い自分と向き合うために
自己肯定感を高めていく方法の基本

自己肯定感を高めていく方法の基本は、これまで基準にしてきた「他人軸」から「自分軸」へと意識をシフトさせることです。そして、自分の長所も短所も含めて、ありのままの自分をまるごと受け入れる姿勢が鍵となります。
これまで自分を否定し続けてきた思考のパターンを、一朝一夕に変えるのは難しいと感じるかもしれません。しかし、人の考え方は、ほんの小さなきっかけで変化することもあります。大切なのは、「こうしなければならない」と自分を追い込むのではなく、まずは自分に意識を向ける習慣を身につけることです。
例えば、誰かから褒められた経験を思い出してみるのも一つの方法です。自己肯定感が低い人は、否定された経験はすぐに思い出せても、褒められた経験は無意識に記憶から削除してしまいがちです。「仕事がうまくいったね」という肯定的な言葉よりも、「この部分はもっとこうして」という指摘の部分だけを心に残してしまうのです。
しかし、あなたは必ず誰かから認められたり、褒められたりした経験があるはずです。最近のことでなくても構いません。過去の成功体験や褒められた記憶を意識的に掘り起こし、「自分にも良いところがある」と再認識する行為が、自分に意識を向ける練習になります。
この「自分に意識を向ける」という行為こそが、自己肯定感を高めていくための全ての土台となります。
思考の癖をリセットする簡単な習慣
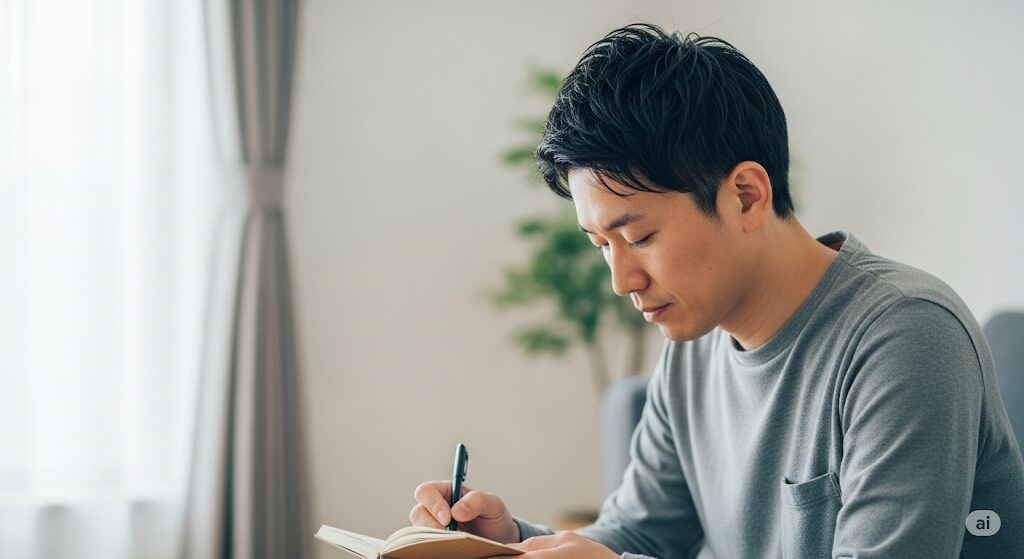
凝り固まった思考の癖をリセットし、自己肯定感を育むためには、日常生活の中で意識的に取り入れられる簡単な習慣が効果的です。脳に新しい刺激を与え、ポジティブな側面に目を向けるトレーニングを行いましょう。
1. いつもと違う行動を試す
生活が単調でマンネリ化すると、脳は次第に活動を停止させ、思考も固定化しがちです。そこで、日常に小さな変化を加えることが、脳の良い刺激になります。 例えば、「いつもより一本早い電車に乗る」「一駅前で降りて歩いてみる」「朝食をパンから和食に変えてみる」といった、ごく些細なことで構いません。いつもと違う風景や体験が、脳を活性化させ、新しい視点を生むきっかけになります。
2. 100日カレンダーで目標を可視化する
何か新しい目標(資格の勉強やダイエットなど)を立て、それを達成するための100日間の計画をカレンダーに書き出す方法も有効です。 「今日は参考書を5ページ進める」のように具体的な行動を書き出し、達成できたらチェックを入れます。目標達成までの進捗が目に見える形になることで、達成感を得やすくなり、着実に前に進んでいる感覚が自信につながります。
3. 良い方に考える癖をつける練習
物事には必ず良い面と悪い面があります。意識的に良い面にスポットライトを当てる練習をしてみましょう。 例えば、身の回りにいる少し苦手な人を思い浮かべ、その人の良いところを無理やりにでも探して書き出してみるのです。最初は難しいかもしれませんが、この練習を繰り返すことで、物事のポジティブな側面を見つける思考回路が養われます。仕事で叱られた時も、「自分への期待の表れだ」と捉え方を変えられるようになります。
これらの習慣は、一度やれば劇的に変わるというものではありません。しかし、地道に続けることで、ネガティブな思考の癖が少しずつリセットされ、自己肯定感を育む土壌が作られていくのです。
ネガティブな感情との上手な付き合い方

自己肯定感を高めるというと、ネガティブな感情を全てなくし、常にポジティブでいなければならない、と考えがちですが、それは間違いです。ネガティブな感情は人間にとって自然なものであり、無理に抑え込もうとすると、かえって心身に悪影響を及ぼすことがあります。
大切なのは、ネガティブな感情を否定せず、その存在を認めた上で、上手く付き合っていく方法を学ぶことです。
ネガティブな感情は「天気」のようなもの
例えば、雨が降っているときに「なんで雨なんだ!間違っている!」と怒る人はいません。天気はコントロールできない自然現象であり、私たちはただそれを受け入れます。 実は、自分の感情もこれと似ています。職場に苦手な人がいて「嫌だな」と感じるのは、ごく自然な感情です。それに対して「こんな風に思う自分は心が狭い、ダメな人間だ」と自分を責めるのは、雨が降っていることに腹を立てるのと同じくらい不毛な行為なのです。
「嫌なものは嫌」「好きなものは好き」。まずは、自分の素直な感情を、良いも悪いもなく、ただ「そう感じているんだな」とありのまま受け入れることから始めましょう。
否定しそうになった時の魔法の言葉
もし、何かミスをして自分を責めそうになったり、ネガティブな感情に飲み込まれそうになったりした時は、「これも私だから」という言葉を心の中で唱えてみてください。 この言葉は、良い悪いという判断を一旦保留にし、否定する思考の連鎖を断ち切る効果があります。うまくいった時も、うまくいかなかった時も、全てが自分の一部であると受け入れるきっかけになります。この言葉を口に出したり、紙に書いたりするのも良いでしょう。ネガティブな感情を無理に消そうとせず、ただ受け流す術を身につけることが、心の安定につながります。
ありのままの自分を受け入れる自己受容

自己肯定感を高める旅のゴールは、完璧な自分になることではありません。むしろ、ポジティブな部分もネガティブな部分も全て含んだ「現実の自分」をありのままに受け入れ、その自分を価値ある存在だと認めること、すなわち「自己受容」と「自己価値」の感覚を育むことです。
自己受容とは何か?
自己受容とは、理想の自分ではなく、今のありのままの自分をそのまま受け入れる力のことです。例えば、「自分は人付き合いが苦手だ」という事実があったとして、それを「ダメなことだ」と否定するのではなく、「自分にはそういう特性があるんだな」と、まずは事実として認めることです。 近年の研究では、この自己受容の感覚が高い人ほど、精神的に安定しており、ストレスへの対処能力も高いことがわかっています。興味深いことに、心理学者のカール・ロジャーズは「自分の現在のありのままを受け入れるとき、自分が変わる」という言葉を残しました。自分を変えようと必死になるのではなく、まず受け入れることが変化の第一歩となるのです。
自分の価値を見つける方法
自己受容した上で、その自分に価値を見出す「自己価値」の感覚も大切です。これは、何か特別な能力や実績があるから価値がある、というものではありません。 例えば、「大きなミスをして落ち込んだけれど、明日からまた頑張ろうと思えている。この立ち直れる力が自分の良いところだ」というように、自分の内面にある強さやあり方に価値を見出す感覚です。
この感覚を育む一つの方法として、「投影の法則」があります。これは、あなたが周りの人に対して「素晴らしい」と感じる魅力は、実はあなた自身の中にも存在する、という考え方です。自分にはないものは、他人の中に見出すことはできないからです。あなたの周りにいる魅力的な友人や同僚を思い浮かべ、その人のどこに魅力を感じるかを考えてみてください。その長所は、形は違えど、あなたの中にも眠っている可能性が高いのです。
自己肯定感が低い自分と向き合うために

この記事では、自己肯定感が低くなる原因から、それを乗り越えていくための具体的な方法までを解説してきました。最後に、これまでの内容を振り返り、あなたが今日からできることをまとめます。
記事のまとめ
- 自己肯定感の低さは性格だけでなく思考の癖や過去の経験が影響する
- 他人軸で考え、自分にダメ出しをするのが低い人の特徴
- 自己肯定感が低いと精神的に疲弊しチャンスを逃しやすくなる
- 根本的な原因は他者評価への依存や過去の失敗体験にある
- 幼少期の親との関係が自己評価の土台に影響することもある
- 恋愛では相手を疑ったり過度に依存したりする傾向が見られる
- 一見プライドが高い態度は自信のなさの裏返しである場合がある
- 高める基本は他人軸から自分軸へ意識をシフトさせること
- 日常に小さな変化を加えることが脳を活性化させ思考を柔軟にする
- 褒められた経験を思い出すなど自分に意識を向ける練習が有効
- ネガティブな感情は否定せず「天気」のように受け流す
- 「これも私だから」という言葉は否定の連鎖を断ち切る助けになる
- ありのままの自分を認める「自己受容」が変化の第一歩
- 周りの人の長所は自分の中にもある魅力(投影の法則)
- 全てのポイントを一度に実践する必要はない


